白浜旅行*アドベンチャーワールド ― 2019-03-01
古賀の井リゾートから、フロントでタクシーを呼んでもらって、アドベンチャーワールドへ。
開場30分前から待機してましたが、金曜にも関わらず、結構人が集まってました。
オープン直後は、みんな彩浜のいるブリーディングセンターに行くので、わーっと人の波について行って並ぶ。とは言っても、10~20分くらいだし、並んでる間もパンダは見られます。
わー、いたいた彩浜~。
丸い…。
基本的に歩きながらの観覧なので、ゆっくりは見られない。
物足りないので、この後もちょくちょく戻ってくることになります。
屋外運動場では、お父さんが優雅に笹を食べていらっしゃいました。
パンダラブの屋内運動場には双子の桜浜と桃浜が。
勝手に、同じ運動場にいるのかと思ってたけど、独り立ちしたパンダは完全分離なのね。
ガラスで区切られた部屋にそれぞれいました。
屋外運動場には結浜。
パンダラブは人がそこまで集まらないので、好きなだけじっくり見られます。
キングペンギンの雛もいる。
保育器にはさらに生まれたての雛も。
またもやブリーディングセンターに。オープン直後よりは列が減ったかな?
遊ぶ彩浜。
眠る彩浜。
12時を過ぎたので、お昼に。
フードコートが混んでいたので、センタードームの丼亭へ。
真鯛の炙り丼。
熊野牛丼。これ、肉が柔らかくて、非常に美味しかったです。
ファーストフード的なジャンクな味ではなく、ちゃんと美味しい和食のお店でした。
丼ものが中心なので、提供が早くて回転もいいみたい。
ケープペンギンのパレードを見て。
またもや彩浜。
しばらくお昼寝中のようで、お客さんもだいぶ減り、フリー観覧タイムでした。
動かないけど、じっくり見られる。
コツメカワウソのふれあいタイムも参加。
これ、場所がログハウス内の休憩所みたいなところなんですが、時間になるまでそれぞれ寛いでいたのに、飼育員さんが動物を連れてやって来ると空気が一変して、みんなさーっと並ぶという、不思議な空間でした。
時間になるまで、「本当にここでやるの?」と不安になるくらいだったのに。
ミーアキャット。
ベニコンゴウインコ。
赤ちゃんパンダの公開は15時までなので、最後にもう一度ブリーディングセンターへ。
考えることはみな同じで、着いた時はフリー観覧でしたが、人が増えてきて、途中で列が作られました。
お昼寝から覚めて動き回っています。
登ったり。
笹を食べる真似。
仰向けでごろごろ。
写真はそれなりに撮れたけど、列を進みながらの観覧なので、ちょっと物足りないな~。
オープン直後とクローズ直前は避けて、お昼過ぎのフリー観覧タイムに、じーっと張り付いていれば、たくさん見られて良かったかも。
事前に公式ツイッターやライブビューイングもチェックしてたけど、やっぱり行かないとよく分からないものだな。
イルカプール。今回は彩浜にかまけて、マリンライブを見逃した。
クジャク。
ショウジョウトキ。
オニオオハシ。
この辺で閉園時間。
写真はないけど、途中でケニア号に乗ってサファリワールドも1周しています。
しかし、広いな~。1日いたけど全然足りない。丸2日回った方がいいね。
この日は晴れていたけど風が強くて結構寒く、うろうろ歩き回って、かなり消耗しました。
最後にワゴンで売っていたシロクマカスタードまん。
パンダまんもかわいかったんだけど、残念なことに売り切れてた。
パンダグッズが何でも揃う土産物屋を覗いて終了。
帰りもタクシーで、古賀の井リゾートに戻ってきました。
この日の夕食はバイキング。
料理自体はどれも美味しく、魅力的でしたが、やっぱり人が多くて取るのが大変。
席が遠くて冷めやすいし、1時間半位で終わってしまうので、のんびりできない。
そんなにたくさん食べられる年齢でもないので、もうバイキングは向いてないかも。
両日とも和食会席が良かったかな?(メニューを変えてくれるのかな?)
EOS M100 ― 2019-03-11
アドベンチャーワールド行きに備えて、EOS M100を購入しました。
これまでは、10年くらい前に夫が買ったEOS Kiss X3を使ってましたが、
若干、挙動があやしくなってきたのと、でかくて重いため、
ミラーレスの方が気軽に持ち出せていいなーと。
デジイチの前に私が持っていたコンデジもIXYで、プリンターもCanonなので、
比較検討も面倒だからCanonでいいかと。
いわゆる「女子カメラ」が欲しかったので、ほぼ一択でM100に。
15-45mmの標準レンズ付きで5万円台。これより高いのはちょっと手が出せないなー。
コンパクトじゃないカメラって初めて買ったんだけど、本体以外のアクセサリーをもりもり買わないといけないんだな!びっくりしたので、下に全部挙げます。
必須のSDカードはどれがいいか分からなかったので夫に丸投げして選んでもらう。
予備があった方がいいかなと、16GBを2枚。
予備バッテリーも要るよなってことで、純正品は高いので、互換品を。
レビューが多かったので選んだ。
それからタッチパネルに保護フィルム貼った方が割れなくていいかと、
種類が色々あって選べなかったので、有名そうなハクバにしといた。
付属品のストラップはCanonのロゴ入りで女子カメラっぽくないので探す。
純正品で、ベージュのレザー製があるけど、幅広で大げさな感じで(軽量カメラだし)。
細幅で、素材はナイロンあたり(レザーより薄くて硬くないもの)、色は黒(汚れが目立たないように)のが欲しかったけれど、M100のストラップホールはベルト幅8mmで、これがあまり売ってない。
幅10mm以上のベルトタイプか、細い紐を通す一つ穴タイプが多い印象。
これなら大丈夫かなーと買ったのが、
ベルト幅が10mmだったので、苦労して無理やり通した。
改めて探すと、
あたりが良かったんじゃないかと…。
純正のレンズキャップは外した後、どこかでホールドしておかないといけないので、
なくさないように紐穴付きの互換品にチェンジ。
これに付いてきた紐が、細いのをただ輪にして通してあるだけで、長いし強度が心配だったので、ストラップパーツに交換。
ただ、キャップを外すとぶらぶらするので、更にクリップも必要かもしれない。
予備のバッテリーとSDカードはモンベルのコインワレットメッシュが丁度よかった。
クッション性がある生地だと思うので、カメラと一緒に入れておいても緩衝してくれそう。
カメラケースはモンベルのプロテクションアクアペル0.5L。
ある程度の衝撃吸収と防水仕様だそう。
平たい袋なので、中身がなければ畳めてコンパクト。
専用品じゃないので、別の用途にも使えそう。
上のワレットを底に入れて、カメラは横向きでギリギリ入ります。
標準レンズだと0.5Lでちょうどいいけど、望遠ズームも使うなら1Lですね。
3回折り曲げてバックルを留めると持ち手ができます。
きゅっとまとめるとカバンにも入れやすい。
諸々アクセサリーを装着して、外に持ち出す時の重量が556gと軽い!
500mlのペットボトルが50ml増量した重さなので、これなら負担にならない。
映画「九月の恋と出会うまで」感想 ― 2019-03-20
「九月の恋と出会うまで」の映画を観てきました。
原作者の松尾由美は以前から読んでいる作家で、本作も新潮文庫の初版を2009年に購入しています。
映像作品を観るよりも、圧倒的に小説やマンガを読んできた人間なので、映画やドラマを観る動機は、「原作を読んでいたから」が一番多いです。以前は「あっ、あの小説(マンガ)映画化するんだ。観なきゃ」と高確率で足を運んでいましたが、幾つか観に行った結果、「やっぱり原作の方が良いな」という感想になるパターンが多く、最近は観る機会も減っていました。
今回は、松尾由美作品の映像化がレアだったため(もしかして初?)、嬉しくなって劇場まで行って来ました。
原作を読んだのはもう10年前なので、内容はほぼ忘れていたのですが、予習ばっちりなのもつまらないだろうと、読み返しなしで映画館へ。鑑賞しながら「そうだ、こういう話だった」と徐々に思い出していきました。
感想は、簡潔に言うと、とても良かったです。
もちろん、小説を映画に変換することによる、いろんな差異はあります。
●原作が2004-2005年だったのを2018-2019年に変更したことによる諸々の設定変更
●小説の方が情報量が多いので、尺を合わせるための、幾つかのややこしい事情の削除
●小説は描写・思考・説明・会話で進むのに対して、映像は表情・動作・風景という「画」を見せるという表現の違い
これらは当然ありますが、全て無理なく収まっていたし、原作の一部を重視するあまり、映画自体のストーリーや理屈が破綻するということもなかった。細かい設定も、ストーリーの流れも、意外なほどに原作に忠実で、最近の原作付き映画はこんなに丁寧に制作するものなのかと驚くくらいでした(単に監督の方針によるものだろうか)。映画ならではの印象に残る映像表現もふんだんで、松尾ファンも喜ぶ良い映画化だったと思います。
そんな映画でしたが、ひとつ、興味深い変更点がありました。
起承転結でいうと「転」のあたり。主人公2人がお互いの気持ちをやり取りするけど、うまく噛み合わず、別離に至る、というシーン。原作では、男性が女性への気持ちをはっきりと口にするけれど、女性の気持ちは別にあり、受け入れられない、という展開です。それが映画では、女性が男性へ(若干婉曲に)気持ちを伝えるけれど、男性が自分に自信を持てず、受け入れられない、という男女の役割の反転がありました。
鑑賞後に改めて原作を読み直し、この相違に気づきましたが、別の作品でも似たようなことがあったと思い出しました。
前述の通り映像作品をあまり観ないので、挙げられるのは1作品だけですが、「逃げるは恥だが役に立つ」でも、同様の変更がありました。
ドラマの最終回直前という最大のヤマ場となるタイミングで、男性が女性に対して、相手への配慮に欠けた提案をしてしまい、2人の気持ちが遠ざかる、というシーン。これが原作では、男性はほぼ似たような提案はしていますが、ドラマほどショッキングな扱いではなく、2人の関係性は良好なまま。ただ、女性が今後の指針を見いだせず、次のステップに進めない、という描写になっています。
2作品とも、原作ではどちらかというと「女性が男性に対してずるい(ひどい)態度をとる/男性は女性に対して真摯」という状況だったのが、映像化作品では「女性には特に非がない/男性が女性にひどい態度をとる」という反転を選択しており、それがとても興味深いと感じました。
どうしてこうなったのかを考察します。
まず、どちらも原作者は女性で、主人公も女性。作者自身が「女性のずるさ・ひどさ」を知っているため、自然に主人公にもそういった行動を取らせてしまう。そして異性である男性の登場人物には、どうしてもファンタジーが入り、理想の男性像的な振る舞いをさせる。このため、2作品とも原作では、「女性がひどい/男性は真摯」という展開になるのではないかと思います。
また、「九月の…」は全編一人称のため、読者は女性主人公の思考をトレースしながら読み進めます。彼女がどんな選択をしても、それを「理解できる」ので、男性にひどい態度をとっても読者は納得して受け入れられます。
「逃げるは…」は主人公以外の内面描写もあるので、「主人公だけを理解している」という状況にはなりませんが、比重としては女性主人公の感情・思考の提示が多く、やはり読者が主人公を受け入れやすいという土壌があります。
一方、映像表現の場合、役者の台詞、口調、表情、動きだけで登場人物の心情を表現します。小説では、感情だけでなく思考も伝えられますが、映画は主に感情を表現していて、(長台詞やモノローグを言わせない限り)思考は伝えられないのではないでしょうか。
そして、本作のように、人気の役者を起用した恋愛映画は若い女性がメインターゲットであり、観客は主人公に共感して鑑賞する、ということが念頭に置かれていると思います。女性主人公に非があると、観客は「なんでそんなことするの」と気持ちが離れてしまい、映画への印象が悪くなる。男性主人公に非があり(しかもそれに至る心情に同情できる)、女性は悪くない、被害者だという状況だと、憤慨せずに物語に浸ることができるのではないでしょうか。
まとめると、
●作者と同性の登場人物の方がリアリティが出やすく、異性の方がファンタジー性を帯びやすい。
●小説・マンガは登場人物の感情だけでなく思考も表現できるため、主人公が良くない行動をとっても、読者は理解し、受け入れることができる。
●映画は登場人物の感情は表現できるけれど、思考は伝達できないため、主人公が良くない行動をとると、観客は良い印象を持たない。
●映画は、メインターゲットとなる観客が感情移入する対象が、悪い印象を持たれないよう計算している。
以上のことから、映画内の見せ場において、男女の役割が反転したのではないかと考えます。それに、よく考えると、女性主人公は特に何もしていないけど、男性主人公がすごく頑張って未来を切り拓いた話のような気もするので、そこでバランスをとったのかもしれません。
まあ、もともと、どっちが悪者になろうと、展開に影響しない小事だと思います。個人的には気にならなかったし(原作をほぼ忘れていたこともあり、観覧中は気付かなかった)。
原作者の松尾由美は以前から読んでいる作家で、本作も新潮文庫の初版を2009年に購入しています。
映像作品を観るよりも、圧倒的に小説やマンガを読んできた人間なので、映画やドラマを観る動機は、「原作を読んでいたから」が一番多いです。以前は「あっ、あの小説(マンガ)映画化するんだ。観なきゃ」と高確率で足を運んでいましたが、幾つか観に行った結果、「やっぱり原作の方が良いな」という感想になるパターンが多く、最近は観る機会も減っていました。
今回は、松尾由美作品の映像化がレアだったため(もしかして初?)、嬉しくなって劇場まで行って来ました。
原作を読んだのはもう10年前なので、内容はほぼ忘れていたのですが、予習ばっちりなのもつまらないだろうと、読み返しなしで映画館へ。鑑賞しながら「そうだ、こういう話だった」と徐々に思い出していきました。
感想は、簡潔に言うと、とても良かったです。
もちろん、小説を映画に変換することによる、いろんな差異はあります。
●原作が2004-2005年だったのを2018-2019年に変更したことによる諸々の設定変更
●小説の方が情報量が多いので、尺を合わせるための、幾つかのややこしい事情の削除
●小説は描写・思考・説明・会話で進むのに対して、映像は表情・動作・風景という「画」を見せるという表現の違い
これらは当然ありますが、全て無理なく収まっていたし、原作の一部を重視するあまり、映画自体のストーリーや理屈が破綻するということもなかった。細かい設定も、ストーリーの流れも、意外なほどに原作に忠実で、最近の原作付き映画はこんなに丁寧に制作するものなのかと驚くくらいでした(単に監督の方針によるものだろうか)。映画ならではの印象に残る映像表現もふんだんで、松尾ファンも喜ぶ良い映画化だったと思います。
そんな映画でしたが、ひとつ、興味深い変更点がありました。
起承転結でいうと「転」のあたり。主人公2人がお互いの気持ちをやり取りするけど、うまく噛み合わず、別離に至る、というシーン。原作では、男性が女性への気持ちをはっきりと口にするけれど、女性の気持ちは別にあり、受け入れられない、という展開です。それが映画では、女性が男性へ(若干婉曲に)気持ちを伝えるけれど、男性が自分に自信を持てず、受け入れられない、という男女の役割の反転がありました。
鑑賞後に改めて原作を読み直し、この相違に気づきましたが、別の作品でも似たようなことがあったと思い出しました。
前述の通り映像作品をあまり観ないので、挙げられるのは1作品だけですが、「逃げるは恥だが役に立つ」でも、同様の変更がありました。
ドラマの最終回直前という最大のヤマ場となるタイミングで、男性が女性に対して、相手への配慮に欠けた提案をしてしまい、2人の気持ちが遠ざかる、というシーン。これが原作では、男性はほぼ似たような提案はしていますが、ドラマほどショッキングな扱いではなく、2人の関係性は良好なまま。ただ、女性が今後の指針を見いだせず、次のステップに進めない、という描写になっています。
2作品とも、原作ではどちらかというと「女性が男性に対してずるい(ひどい)態度をとる/男性は女性に対して真摯」という状況だったのが、映像化作品では「女性には特に非がない/男性が女性にひどい態度をとる」という反転を選択しており、それがとても興味深いと感じました。
どうしてこうなったのかを考察します。
まず、どちらも原作者は女性で、主人公も女性。作者自身が「女性のずるさ・ひどさ」を知っているため、自然に主人公にもそういった行動を取らせてしまう。そして異性である男性の登場人物には、どうしてもファンタジーが入り、理想の男性像的な振る舞いをさせる。このため、2作品とも原作では、「女性がひどい/男性は真摯」という展開になるのではないかと思います。
また、「九月の…」は全編一人称のため、読者は女性主人公の思考をトレースしながら読み進めます。彼女がどんな選択をしても、それを「理解できる」ので、男性にひどい態度をとっても読者は納得して受け入れられます。
「逃げるは…」は主人公以外の内面描写もあるので、「主人公だけを理解している」という状況にはなりませんが、比重としては女性主人公の感情・思考の提示が多く、やはり読者が主人公を受け入れやすいという土壌があります。
一方、映像表現の場合、役者の台詞、口調、表情、動きだけで登場人物の心情を表現します。小説では、感情だけでなく思考も伝えられますが、映画は主に感情を表現していて、(長台詞やモノローグを言わせない限り)思考は伝えられないのではないでしょうか。
そして、本作のように、人気の役者を起用した恋愛映画は若い女性がメインターゲットであり、観客は主人公に共感して鑑賞する、ということが念頭に置かれていると思います。女性主人公に非があると、観客は「なんでそんなことするの」と気持ちが離れてしまい、映画への印象が悪くなる。男性主人公に非があり(しかもそれに至る心情に同情できる)、女性は悪くない、被害者だという状況だと、憤慨せずに物語に浸ることができるのではないでしょうか。
まとめると、
●作者と同性の登場人物の方がリアリティが出やすく、異性の方がファンタジー性を帯びやすい。
●小説・マンガは登場人物の感情だけでなく思考も表現できるため、主人公が良くない行動をとっても、読者は理解し、受け入れることができる。
●映画は登場人物の感情は表現できるけれど、思考は伝達できないため、主人公が良くない行動をとると、観客は良い印象を持たない。
●映画は、メインターゲットとなる観客が感情移入する対象が、悪い印象を持たれないよう計算している。
以上のことから、映画内の見せ場において、男女の役割が反転したのではないかと考えます。それに、よく考えると、女性主人公は特に何もしていないけど、男性主人公がすごく頑張って未来を切り拓いた話のような気もするので、そこでバランスをとったのかもしれません。
まあ、もともと、どっちが悪者になろうと、展開に影響しない小事だと思います。個人的には気にならなかったし(原作をほぼ忘れていたこともあり、観覧中は気付かなかった)。
















































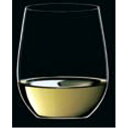
















最近のコメント